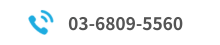先月から今月頭にかけて、研修の運営が多かったのでてんてこ舞いでした。
久しぶりの更新ですが、今回は思惟、個人の思考についての対立の関係、
つまり「二項対立」について、ちょっと難しい話をしてみようかと思います。
二項対立とは、論理学用語ですが、詳しくはネットに載っていますので、割愛。
世の中の物事が、
だいたい対立する二つの概念で形成されているのは今更の話なのですが、
例えば、「陰と陽」とか、「明るい暗い」とか、
「男と女」とか、「メリットとデメリット」とか、
まあ挙げていけばキリがありませんが、これは、個人の思考にも当然当てはまります。
特に教育の分野に関わる人は、
このコンフリクトを起こす二項対立を知っていないと、
少し危険なことになると個人的には思っています。
危険なこととはどういうことかというと、
今でいえば認知バイアスなんて言葉もありますが、
何かを人に説く人には、必ずその言説に「信を置く」構造を持っています。
つまり、何かを信じたり(一時的にでも)、
拠り所にしたりして他人に説法をするわけです。
しかし、この信を置くこと自体が一方通行で問題なことが多く、
Aを肯定することで、Bが否定されるという側面があります。
例えば、ロジカルシンキングの指導をしている人なんかは、
「論理的」という面に「信」を置いて講話をするので、
それによって「非論理的」という側面が否定されてしまいます。
これが二項対立という面での危険性で、
人間は論理的であることもできるし、非論理的であることも本来は両方ある、
つまりある意味では自由な存在といえますが、
論理的であることに信を置きすぎてしまうと、
今度は非論理的・非合理的な思考回路に対して、
否定したり、理解できなかったり、もっとひどいと拒絶したりしてしまうのです。
これが思考のもつ二項対立における危険性です。
そして、信を置く度合いが強くなると、
それが最終的には強迫性を帯びた観念となり、
自分の思考にこびりついて離れなくなります。
なので、必ず二項対立があるということを念頭に置いておかないと、
その人の思考や思想は、本当のことを言っておらず、
怪しい面があるということになります。
今世間を騒がせているカルトの問題も似たようなものです。
宗教的な思想は「信を置く」という構造がベースにあるので、
それ以外の思想に対して、排他的な態度を取りえる、
というか取らざるを得ない立場になる可能性を持っています。
もちろんこれは宗教だけでなく、全世界で日常的に行われている言説であれば、
どれでも当てはまるでしょう。
なので、特に人を指導する立場にある人は、
この二項対立という概念は、
頭の片隅にでも入れておいたほうがいいと思っています。
曲解の発生
さて、そこでさらに問題になってくるのが、
今度は「曲解」です。
これは言動や言説に対しての解釈の問題になりますが、
人間は、誰でも、いつでも曲解する可能性を持っています。
例えば、「偉い人」という言葉を聞いたら、皆さんはどんな人を思い浮かべますか?
個人の「偉い」という概念の捉え方で変わるかも知れませんが、
一般的に思いつくのは、
地位や身分が高いとか、お金があるとか、権力があるとかでしょう。
社長なんかが良い例かも知れません。
話は変わって数十年前に、
アメリカからCS(customer satisfaction)という概念が日本にも入ってきました。
いわゆる「顧客満足」という概念ですが、
今では企業内では一般的になりましたが、
言説の危険性としては、日本でいうと「お客様は神様」といううがった概念として、
曲解を発生させる可能性があります。
先に出た「偉い」という概念に「お金がある」が結びついてしまっていると、
「お金をもっている」=「偉い」という曲解の構造が、
自分でも気づかない内に発生してしまっている可能性があり、
もともとの顧客満足も、曲解すればこういううがった思考にも発展する概念です。
コンビニやショップなどで、偉そうな態度で店員に接している人、
上から目線で他人と接する人を最近よく見ますが、
曲解の良い例か、その人の精神的な問題なのかのいずれかでしょう。
というか、ここまで書いてきて、
今私が書いているこの内容がすでに曲解かもですが(笑)
だんだん自分で書いていてもちょっと難しくなってきたので、
今日はこの辺でやめておきます。
とにかく、曲解はともかく、
二項対立の危険性ということを強調したかった本日です。